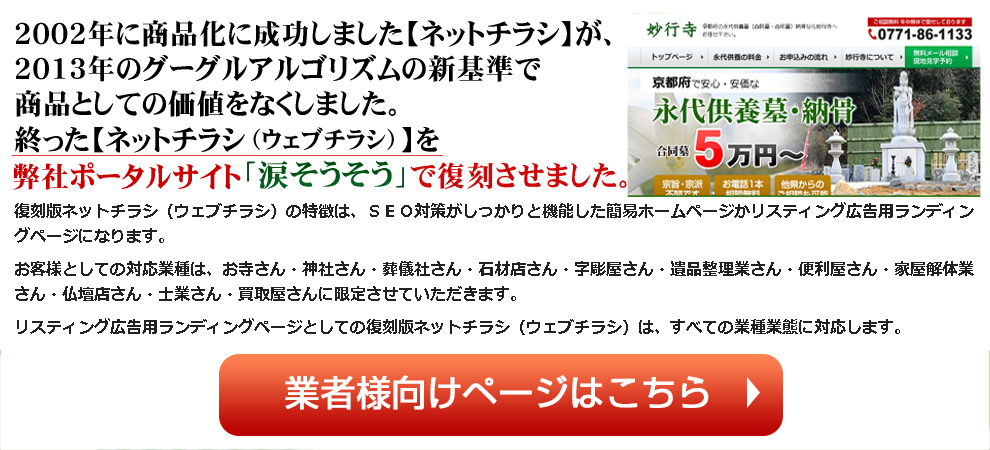平成28年4月に多治見市大藪町に開設された 多治見市火葬場「華立やすらぎの杜」。
「心の和む空間、やすらぎを与える尊厳のある葬送の場」をコンセプトに、緑地帯や修景池を設置し周辺環境との調和、景観に配慮。
また、随所に美濃焼タイルを用いて、多治見らしさを表現した施設。
火葬場には、貸し葬儀式場が併設。家族葬から一般葬まで葬儀式を執り行えます。
シンプル葬祭は、華立やすらぎの杜 貸し葬儀式場での葬儀施行実績件数NO.1です。(令和1年12月現在)
華立やすらぎの杜で葬儀式をお考えのお方様は、お気軽にシンプル葬祭までお問い合わせください。

| 名称 |
多治見市火葬場 華立(はなたて)やすらぎの杜 |
| 所在地 |
多治見市大薮町字上迫間洞249番地 |
| 構造 |
鉄筋コンクリート及び鉄骨造 |
| 敷地面積 |
20,126.99㎡ |
| 建築面積 |
3,180.12㎡ |
| 延べ床面積 |
2,910.86㎡ |
| 建物高さ |
16.12㎡(最高部) |
| 主な部屋 |
式場,食事室,お別れ室(6),待合室(3) |
| 炉数 |
火葬炉(6炉),多目的炉(1炉) |
| 駐車場 |
143台(身障者用、マイクロバス用含む) |
はじめに
≪ お葬式は、誰のために? ≫
お葬式、それは人が死んだ時、その方の冥福を祈るとともに、最後のお別れをする為の儀式です。歴史的には、地域の人たちみんなで、野辺(村はずれの埋葬する場所)まで送って行ったことが、お葬式のはじまりだとされています。
それが、時代ととともに変化し、現代のようなかたちになりました。
ところで、お葬式というものは、誰のために行うものなのでしょうか?
まずに、お葬式は「亡くなった人のため」に行うものです。亡くなった人に想いをはせ、仏教では供養を、神道では鎮魂(ちんこん)をキリスト教では追悼を行うのがお葬式です。あの世に行っても幸せに暮らせることを祈るためと言い換えてもいいのかもしれません。
また、お葬式は「家族のため」に行うものです。人が亡くなって一番悲しむのは家族です。その家族が、故人とお別れをするための儀式がお葬式なのです。
さらに、お葬式は「友人知人のため」に行うものです。人間は、社会的な動物で、いろいろな人と関わりを持ちながら生きています。年代ごとの友人、職場や地域の人など、様々な人たちに支えられています。お葬式は、そうした人たちと最後のお別れをするための儀式でもあるのです。
その1【葬儀の分類】
| 【参列する人による分類】 |
| 社葬 |
会社等の組織が施主となり会社関係者が広く参列する葬儀。 |
| 一般葬 |
遺族が施主となり親族・知人友人等が広く参列する葬儀。 |
| 家族葬 |
家族葬・一日葬・直葬の形式で家族・親族のみで行う葬儀。 |
| 【葬儀の形式による分類】 |
| 一般葬・家族葬 |
通夜式・葬儀式を執り行う |
| 一日葬 |
葬儀式のみ執り行う(通夜式を行わない) |
| 直葬 |
通夜式・葬儀式を行わない。 |
| 【宗教による分類】 |
| 仏式 |
寺院(僧侶)が導師となり葬儀式を執り行う。 |
| 神式(神道式) |
神社(宮司)が祭主となり葬儀式(祭祀)を執り行う。 |
| キリスト教式 |
神父または牧師が祈り葬儀式を執り行う。 |
| 無宗教式 |
宗教者が宗教的儀式を行わず、参列者代表などが弔辞などを述べお別れ式を行う。 |
| 【場所による分類】 |
| 葬儀式場 |
葬儀会社直営式場、公営貸し式場、民営貸し式場 |
| お寺・教会 |
寺院内の式場、教会内の聖堂 |
| 自宅 |
故人・親族の自宅 |
| 集会場 |
自治会等の管理する集会場など |
| ホテル・ホール |
ホテルやイベントホール(社葬などの大規模葬儀) |
| その他 |
高齢者施設など |
その2【家族葬・直葬の定義】
1.「家族葬」とは
一般の葬儀のように関係者であれば誰でも自由に参列できるということではなく、
「ゆっくりとしめやかに、家族や身内だけで別れのときを過ごしたい」
「葬儀の準備や手配にふりまわされず静かに故人を偲びたい」
「義理の会葬に気をつかわず、心から悲しんでくれる人だけで送りたい」
などの想いで、あらかじめ限られた家族や親戚、ごく親しい友人でゆっくりと行われる葬儀です。
つまり家族葬とは、「社会的な儀礼より、故人との別れを最優先する葬儀」となります。
また、少子高齢化・近所付き合いの希薄化などの理由により、そもそも葬儀に参列する親族・友人・知人が少ない為に小規模な葬儀になってしまうケースが多くみられます。
≪ポイント≫
- ※「家族葬」は、葬儀の様式・儀礼、宗教形態を何ら規定するものではありません。
- ※「家族葬」は、参列者の人数や関係性を何ら規定するものではありません。
- ※ 一般葬の小規模な葬儀が家族葬となっていることが少なくありません。
2.「直葬(ちょくそう)」とは
お葬式は本来、通夜⇒葬儀・告別式⇒火葬という流れで執り行われるのが一般的ですが、儀式的なこと(葬儀)は行わず、火葬のみを行うことを直葬と言います。(火葬式とも言います)
亡くなった後、ご自宅、斎場や遺体保管施設(霊安室)に24時間以上安置した後、火葬します。
火葬炉の前で僧侶等により簡単に読経をあげてもらう等の宗教儀礼を行う場合もあります。
3.「密葬」とは
「故人を茶毘に伏すにあたり、家族・親族をはじめとした近親者のみで葬儀を行い、後日、一般参列者を招いて「本義」(社葬・お別れ会など)を行う前提で執り行われる葬儀」となります。
※「荼毘」とは、死体を焼いて弔うという意味です。
その3【家族葬を行うときの”注意点”】
1.葬儀に参列してもらう人(範囲)を明確にすること。
- 【家族葬を行う際の "参列してもらう範囲" 事例3タイプ】
- しっかりと車前に家族構成や交友関係を調べ、呼ぶ人(範囲)を相談して明確に決めておくことが大切です。
事例として家族葬を行う際に連絡をする人、参列してもらいたい人は次のような3つのタイプが多いようです。
- 事例① 遺族のみ (1親等の範囲 配偶者・お互いの両親・子供)
- 事例② 遺族 + 親族 (2親等の範囲)
- 事例③ 遺族 + 親族 + 親しい友人 (故人の関係)又は近所
- 【故人を大切に想う人は家族だけではない。】
- 親戚の方の中でも、それぞれの方が故人に対しての特別な想いを持っています。友達関係でも、故人には故人の付き合いがあり、仲が良かった方々は最後のお別れをしたいと思うのが普通なことです。
そのような故人を囲う人たちへの配慮も必要です。
2.ご遺体安置場所を決める。
近年は、病院・施設等で最期を看取るケースが大変多くなっています。その場合、病院・施設ではご遺体を通夜式まで(長時間)安置をしてもらえません。
よって、ご遺体をご自宅またはご遺体安置施設(葬儀式場等)へ移動し安置しなくてはなりません。
ご自宅で通夜・葬儀式を執り行っていた当時は、ご自宅でご遺体は安置していましたが、近年は通夜式・葬儀告別式を葬儀会館(葬儀式場・ホール)で執り行うことが主流となり、ご遺体はご自宅ではなく、遺体安置施設(葬儀式場等)で安置するケースが多くなっています。
- 【ご自宅に安置される方の理由】
-
- 故人は、病院・施設での生活が長くいつも家に帰りたいと言っていたので自宅に帰してあげたい。
- 故人も家族も住み慣れたご自宅でお別れの時間をゆっくり過ごしたい。
- 近所の方にお別れをしてもらうことが出来る。
- 【遺体安置施設(葬儀式場等)に安置される方の理由】
-
- ご自宅には、物理的にご遺体の搬入・安置ができない。
- 故人は、病院・施設での生活が長く帰る家が既にない。
- 近所の方に知らせず、静かに葬儀式を行いたい。
3.内容を明確にすること。
家族葬で行う場合、ご遺族様のご意向で弔問会葬(参列)や香典・供花供物など辞退(ご遠慮)をされる場合があります。
弔問会葬(参列)、ご香典(御霊前・御仏前)ご供花ご供物など、葬儀後の事も含め、「どこまで受けるか?」内容を明確にする必要があります。
家族葬と聞いた方は「弔問参列に行って良いのか?」「香典は出して良いのか?」「お供えのお花は受け取ってもらえるのか?」・・など、どのように対応してよいか迷われるケースが多々あります。
| 香典 |
家族・親族 |
何も言わない(受取る)orお断りする(受取らない) |
| 家族親族以外 |
何も言わない(受取る)orお断りする(受取らない) |
| 供花供物 |
家族・親族 |
何も言わない(受取る)orお断りする(受取らない) |
| 家族親族以外 |
何も言わない(受取る)orお断りする(受取らない) |
弔問
(安置時・通夜) |
町内 |
断らないorお断りする |
| 友人 |
断らないorお断りする |
| 会社関係 |
断らないorお断りする |
会葬
(通夜式・葬儀式) |
町内 |
断らないorお断りする |
| 友人 |
断らないorお断りする |
| 会社関係 |
断らないorお断りする |
実際に起こったトラブル
- 故人の親友一人だけに連絡したら、友人が多数通夜式に来られた。
- 親族も含め全ての方に香典を辞退したが、親族からの香典は断りきれず気まずくなった。
- 葬儀後に自宅へ香典をもって弔問にこられ、お返しの品を用意してなくて対応できなかった。
- 親族のお供えを断っていたが、一般の方からお花が届き気まずい思いをした。
≪ポイント≫
連絡を受けた方が、「どうすればよいのか・・・?」と、迷わないように内容を明確にし、はっきりご案内することが重要です。
4.報告をする(事前報告)(事後報告)
- 【故人・家族の意向をしっかり伝える】
亡くなった時点でどの範囲まで訃報連絡をすれば良いのかを把握することが重要です。
「家族葬=家族以外にはお知らせしないで済む葬儀」ではありません。
親戚や近隣の人など、お付き合いのある方に"家族だけでゆっくり送りたい旨"を理解してもらうことが重要です。
その理解が得られないと感情的なしこりを残すことにもなりかねませんので、事前にその旨を伝えておく必要があります。
近年、葬儀式前に訃報連絡を行わず、葬儀式が終わってから事後報告されるケースも増えてきました。
≪ポイント≫
意図しない捉えられかた(誤解)をされては、今後のお付き合いに支障をきたしてしまいます。 お付き合いのある方へは、家族葬で行う事を必ず理解してもらうことが重要です。
さらに、「一般参列者はご遠慮いたします。」「ご香典、御霊前、御仏前、ご供花・ご供物」なども辞退する」など、はっきりと確実に伝えることが重要です。
「事前報告」の場合は緊急を要しますので、会社関係などはFAXや電子メールを利用し、近所であれば、自治会で回覧していただくと良いでしょう。
5.家族葬と無宗教葬は別物
- 無宗教葬儀(無宗教式)とは
- 特定の宗旨・宗派の宗教儀礼によらない葬儀を行うことを「無宗教葬」と言いい宗教を否定しているものではありません。
≪無宗教葬儀の一般的な式次第≫
- 開式の言葉
- 黙祷献奏(思い出の曲など)
- ナレーション(故人の経歴など)
- スライド・DVD・ビデオの上映
- お別れの言葉
- 献花
- 閉式の言葉
≪ポイント≫
遺族、親族間でトラブルにならないように事前に打合せをしておく必要があります。
無宗教式は、ご遺族様のお別れの言葉(弔辞)、また故人様ご家族様の写真・動画 、エピソード等のご提供が必要な場合があります。どのような式にしたいのかをしっかりイメージしていただく必要があります。
その4【家族葬”その後の対応”】
≪会葬をご遠慮していただいた方への配慮≫
- 【報告をしっかりする (事後報告)】
- 事前に家族葬で執り行う旨をお伝えし、会葬をご遠慮していただいた方へは「家族葬にて執り行いました」という報告と、生前故人がお世話になった御礼を書面にてお伝えすると良いでしょう。
また年末の喪中ハガキにその事を書き添える場合もあります。
- 【お参りを希望される方が多い場合】
- 葬儀後、ご自宅へ弔問にみえる方が必ずいらっしゃいます。
故人の生前の交友関係の広さや社会参加の程度によっては、個別に自宅での対応が非常に難しくなります。
その場合は、お別れ会を開くなど、故人を偲ぶ事が出来る場を改めて設けると良いでしょう。
- 【返礼品は、四十九日までにお届けすれば大丈夫。】
- 香典返しは香典を頂いた時にお返しする「即返し」が一般的な地方もありますが、葬儀後に香典等を頂いた場合は、即返しができなくとも失礼には当たりません。
四十九日までの間に返礼品(忌明けの引出物)を準備し、改めてお礼をしましょう。
- 【新聞掲載は控える】
- 新聞の「お悔やみ(死亡)掲載」は、喪家により "する・しない"を選択できます。
掲載をすると、思いがけない方がご自宅へ弔問に来られることがあります。また、仏壇・ギフト・法要に関する業者から多数の営業が来ますので注意しましょう。
その5【家族葬”費用は安いの?”】
1.葬儀費用の内訳
葬儀の費用は一般的に「葬儀費用」「変動費用」「お布施」の3つに別れます。
一般的に葬儀社のいう「葬儀費用」というのは、葬儀にかかるすべての費用と言うわけではありません。
宗旨、地方の慣習によっても葬儀費用に含まれるサービスや商品の内容は異なります。

- 【葬儀費用とは】
- 通夜式・葬儀式を執り行うにあたって必要な品物、施設・設備・サービスに対して、葬儀社に支払う基本葬儀料金のことです。
葬儀費用に含まれる品物、施設・設備・サービスは、葬儀社によってかなり違いがありますので見積書などで事前に明細をしっかり確認しておきましょう。
(式場利用料・祭壇・棺・枕飾り・ドライアイス・人件費など)
- 【変動費用とは】
- 葬儀費用に含まれない物品・利用・サービス料のことです。
- 会葬者の人数等で変動する接待費用。
(会葬返礼品、香典返品、料理、供花供物、その他)
- 喪主様のご意向で必要な物品サービス、またはグレードアップで変動する費用。
(納棺師による納棺の儀・湯灌、霊柩車、送迎バス、駐車場警備員、寝具、その他)
- 【お布施とは】
- 読経や戒名(法名等)の授与等に対してお寺(宗教者)へ払う謝礼となります。お布施とは別に、心づけ、お車代、お膳料などが別に必要な場合があります。
2.家族葬では、返礼品・食事の費用が抑えられる。
家族葬の場合、家族中心という少人数で葬儀を行うので、返礼品や食事といった、人数によりかさむ費用は抑えられます。
しかし、一般的な葬儀の場合、葬儀費用の支払いは[喪家負担+香典収入]となり、何割かを頂いた香典で費用捻出することが可能ですが、家族葬においては香典が少なくなるため、一般的な葬儀をした場合以上に、喪家の負担が大きくなってしまうケースもあります。
3.葬儀費用の金額掲載に要注意
葬儀社のチラシなどに掲載されている、「葬儀費用○○○万円」には、プランに含まれる内容が各社オリジナルですので、単純に料金比較をすることができません。
≪プランに含まれない費用≫
「○○プラン ○○○万円」という葬儀プランに「葬儀プランに含まれるもの」と掲載のあるチラシを良く見かけます。
一見プラン内容で葬儀が全て行えると思いがちですが、殆どの場合、「プランに含まれるもの」だけで葬儀費用は済みません。
「プランに含まれていないもの」がありますので、ご注意ください。
≪追加料金≫
「葬儀プランに代金含む」と掲載があった項目でも最終的に追加料金を請求されることがあります。
- 「ドライアイス 2日目・3日目分 追加」
- 「ご遺体搬送 夜間割増追加」
- 「安置所(ご自宅)から式場までの搬送 別途追加」
- 「通夜式前日分のご遺体安置料 別途追加」
など。
4.家族葬の葬儀費用が100万円を超えることも。
参列者10名の家族葬が参列者100名の一般葬の葬儀費用の1/10になるわけではありません。
式場の広さ・設備・祭壇によっては、家族葬も一般葬もほとんど葬儀費用が変わらない場合もあります。
葬儀社で事前相談、事前見積りなどを行い、どれくらいの規模で、どれくらいの予算で家族葬を行いたいのかを事前に決めておくことが必要です。